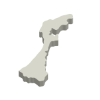クリスマス・キャロル
提供元:金沢大学男子バスケットボール部
2024/12/27 01:18
どうも
クリスマスイブに高熱を出し寝込み、そのままクリスマスはベットの中だけで過ごしました
2年の後藤です。
またの名をごっそと言います。( ¯꒳¯ )ノドモドモ
やっと熱が下がりました。_( _´ω`)_フゥ
あとは寝すぎによる腰と尾てい骨の痛み、あと体の気だるさを乗り越えることが出来たら、またいつものように暴れ回ることが出来そうです。
バタバタ(((((└(:D」┌)┘)))))))
体調心配してくれたり、飲み物とか色々買ってきてくれた人達には感謝してもし足りないくらいです。
ありがとうございました。 (ㅅ´꒳` )
さてさて
もう過ぎちゃいましたけど、せっかくクリスマスの時期にブログの順番が回ってきたので、今回のテーマはディケンズとスクルージでいきましょう。
あー、あれです、小説『クリスマス・キャロル』です。
まぁ僕も高校の宿題で英語でしか読んだことないので、詳細なとこはあんまり覚えていません。
あ、そうです。英語の小説です。イギリス文学です。
簡単なあらすじはこんなかんじ。
金儲け一筋の商売をする非情で冷酷な主人公スクルージはクリスマス・イブの夜、ある不思議な体験をすることになる。
それはぽっと出の三体の精霊にそれぞれ過去、現在、未来の様々な姿を見せられるというものだった。
しかしこの出来事からスクルージの人生観は変わり、貧しい人を助けたり、部下の給料を上げたりするなど、とてもいい人になったとさ。ちゃんちゃん。
と、非常に起承転結の綺麗な小説です。
でもこの小説を読んだ時に、僕が思ったのは、スクルージの人生観が変わるのに過去と現在を見せた精霊って必要だったのか?
ってとこでした。
何となく考えてみると、この手の小説での改心パターンって主に2つあると思います。
1. 自分が過去にやってきたことや、今やっていることによって何か多くの人の不幸を作っていることに気づくこと。
2. 同じく過去や現在の言動によって自分の悲惨な未来の姿が映し出されて、そうならない為に頑張ること。
1に関しては物語の中でスクルージは恵まれない人々への寄付を募りに来た紳士たちに「恵まれない奴らは牢屋や救貧院に入ればいい」とか「恵まれない奴らが死ぬことになれば余分な人口が減って丁度いい」とか言う程の考え方を持つタイプですから、このパターンは関係なさそうです。
であれば、考えるべきは2のパターンのみになります。
実際、3体目の精霊がみせた未来は、周囲からの評判が悪く誰にも悲しまれることも見守られることも無く死に行き、その死後も誰も見舞いに来ない見捨てられた墓碑に眠る自身の姿だったわけですし。
でも精霊たちが見せた過去、現在はこれにほっとんど関係がないものなんですよねー。
だからやっぱこの精霊が三体いるという必要性は結構考えてもなんだか疑念が残るものでした。
しかしこの小説の最も大事なポイントはこの小説の全体像と時代背景、そして作者ディケンズの過去を照らし合わせて見ていくことだと思います。
あーもう長いですね。
まだ折り返してもいませんが。
『クリスマス・キャロル』が出版されたのは1843年の12月。ディケンズの出身地はイギリスです。
さてイギリスでこの少し前に興った18世紀後半から19世紀初頭にかけて起こったことといえば!
伊勢先生!答えをどうぞ!
やはり流石です。
教師の卵の鏡とは本当にあなたのような人のことを言うのだと思います。
そうですよね、産業革命です。
あのー、あれですよ。
ワットさんが開発した蒸気機関がなんとかかんとかってやつです。
そしてイギリスと言えば、もう一つ。キリスト教という括りの中でも、プロテスタントであることが有名です。
まぁ何が言いたいかってーと、「働かざる者食うべからず」とか聖書に従った考え方が当時は強かったり強くなかったりしたわけです。
その結果生まれた現象がヴィクトリア朝の全盛期、低賃金、劣悪な労働環境に悩まされる工場労働者による街のスラム化とマルサスの救貧法の廃止の提言です。
実際ディケンズは作家になる前、12歳の頃から一家の破産を理由に過酷な労働生活を経験している身ですし、この街のスラム化を間近で見てきた張本人であることは間違いありません。
それと、救貧法とはなにか。
まぁ簡単に言うと税金を使って教会が貧困者の生活を支えようと、ご飯くばったりするやつです。
いわゆる、社会福祉制度ですね。
ところが、マルサスはばっちばっちの優生論者。生活保護は怠け者を増やすんだから、貧者は人口抑制しようぜって言う始末。
実際にこの救貧法は廃止されてしまいます。
この世の中に対して小説という形で批判する態度を示したのが、この『クリスマス・キャロル』だという訳です。
この小説の中ではスクルージが当時の資本家たちやその他お金を持つ政治家等を指すと考えると、スクルージの小説の頭と尻の考え方の変化は、頭が現在の状況、尻が本来あるべき彼らの姿を指していると言えると思います。
まぁこれはあらすじに書いてあるとおりですね。
つまり貧しい人達に手を差し伸べるようになっているというわけです。
ではさっき話した通り精霊たちがみせた過去、現在を示したことの意図はどこにあるか。
何となくそれぞれの概略を見ると
過去は青年時代に働いていたところの雇い主がクリスマスに舞踏会を開き、自身がそれを見ることが出来ていたこと。
そしてその数年後に恋人から「今のあなたは私よりお金が大事になってしまい愛していた頃とは別人だ」という理由で別れを切り出されたこと。
などになります。
現在はクリスマスイブの夜、貧しいながらも明るく楽しい食事会をしている家の様子を見るというものです。
スクルージをお金持ちの象徴だと改めて考えると、雇用主に大事に扱われていた過去があっても、それを忘れたようにお金に目が眩んで愛を手放す姿、そして貧しくても楽しむ様子と自分の現在の孤独な様子の対比された姿から比喩的、客観的に今の資本家の様子を描こうとしているような気がします。
こんな風に考えると小説『クリスマス・キャロル』はやっぱ綺麗な小説の中に様々な感情の入った小説なのだろうなと推察できます。
さて、こんな長いブログを読んでくださっている方々がいることを信じて最後まで書かせて頂きます。
ここまで読んでくださってるだけで本当に感謝です、ほんとうに。
ディケンズのすごいところは、かなり勤勉であったこと。
自身の小説が売れ、出世街道の道を進んだのに、人気のほとんどは一般大衆、つまり貧困層だったり貧困ではないにせよお金持ちとは呼べないような人達からのものだったことです。
自分の努力で徐々に自身の地位を上げて作家になり、気づいたらそこで自身の小説で社会制度批判(あまり知りませんが、他の小説でも同じような事をやっているようです)
自分の歩んできた道のりを忘れず、奢らず誰か他の人のためにもなるような小説を書く。
なんとも素晴らしい方です。
別にスポーツにだって通用する考え方だと思いますし、チーム作りにも大事な考え方だと思います。
新チームが指導して2ヶ月。
数字にすると短いようだけど、されど2ヶ月とは言えるような気がします。
まずは少しづつ勤勉にがんばる。
多分、色んな話があって、色んな考えが頭の中でごちゃっとして、逡巡があったり、決心したものがあったり、人それぞれだと思います。
そういう時は今は時間もあるし、ゆっくり今の状態を整理して、深呼吸して、すこーしいつもよりがんばるをしていけたらいいのかなと思います。
と、体調不良者が言ってます。
(・ε・` )チェッ
小耳に挟む程度で聞いといてください。
最後に、スクルージが物語の最後で心に留めていた言葉です。
何かを変えようとすると最初は笑われるものだ。
まぁまずは何かしら変えようとちょっと頑張るところからですね。